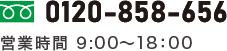平成24年8月 気になる話題
投資促進税制見直しでデジタル複合機がピンチ
中小企業投資促進税制は、中小企業が、新品の機械・装置、器具・備品等の設備を取得し一定の事業の用に供した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用を認める特例制度です。
24年度税制改正では対象設備の一つであるデジタル複合機については、従来の「1台あるいは複数台合計で120万円以上」という要件が見直され、「1台120万円以上」となって、24年4月1日以後の取得から適用されているので注意が必要です。
24年度税制改正では対象設備の一つであるデジタル複合機については、従来の「1台あるいは複数台合計で120万円以上」という要件が見直され、「1台120万円以上」となって、24年4月1日以後の取得から適用されているので注意が必要です。
国民年金保険料の後納制度
未払いの国民年金保険料がある場合には、従来より過去2年分までは遡って保険料を納付することができるようになっています。
これが、24年10月1日から27年9月30日までの3年間に限り、過去10年分まで遡って納めることができるようになります。過去3年度分を超える期間の保険料を後納する場合には、保険料額に加算金額を加えたものを納付する必要があります。
これが、24年10月1日から27年9月30日までの3年間に限り、過去10年分まで遡って納めることができるようになります。過去3年度分を超える期間の保険料を後納する場合には、保険料額に加算金額を加えたものを納付する必要があります。
非居住者等に係る源泉徴収
近年の国際化に伴い非居住者や外国法人に対して支払う源泉徴収でのミスが少なくありません。
具体的には、非居住者等から日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる場合に支払う賃借料は源泉徴収する必要がある一方、個人が自己又はその親族の居住の用に供するために土地や家屋を借りる場合に支払うものについては、源泉徴収の必要はありません(法人が借りて賃借料を支払う場合を除きます)。
また、国内において業務を行う者が非居住者等に支払う工業所有権や著作権等の使用料又はそれらの取得の対価のうちその国内業務に係るものや、非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対するものについても、源泉徴収しなければなりません。
具体的には、非居住者等から日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる場合に支払う賃借料は源泉徴収する必要がある一方、個人が自己又はその親族の居住の用に供するために土地や家屋を借りる場合に支払うものについては、源泉徴収の必要はありません(法人が借りて賃借料を支払う場合を除きます)。
また、国内において業務を行う者が非居住者等に支払う工業所有権や著作権等の使用料又はそれらの取得の対価のうちその国内業務に係るものや、非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対するものについても、源泉徴収しなければなりません。
中間納付等還付加算金の計算期間変更で33億円節約
税務署長が国税を還付する場合、所定の日の翌日から還付金や過誤納金の支払決定日までの期間に応じて計算した還付加算金を付して還付することとされています。
しかし、還付加算金の計算期間に税務当局が還付金の発生を認識できないなどの期間が含まれているため、還付加算金が多額に支払われる事態が見受けられました。
24年1月1日より、確定申告により確定した法人税及び消費税が更正に基づき中間納付額等の還付金として還付される場合の還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数はその計算期間に算入しないこととされました。その結果、還付加算金が33億円減少すると推計されています。
しかし、還付加算金の計算期間に税務当局が還付金の発生を認識できないなどの期間が含まれているため、還付加算金が多額に支払われる事態が見受けられました。
24年1月1日より、確定申告により確定した法人税及び消費税が更正に基づき中間納付額等の還付金として還付される場合の還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数はその計算期間に算入しないこととされました。その結果、還付加算金が33億円減少すると推計されています。
高額療養費の現物給付化
高額療養制度は、1ヶ月間に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が高額となった場合、申請を行うことで後から自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。
19年4月から入院について、窓口での支払を自己負担限度額までとする現物給付化が行われていましたが、24年4月1日からは外来診療についても現物給付化が始まりました。
高額療養費の現物給付化の適用を受けるためには、事前に限度額適用認定証の申請をしておき、それを医療機関等の窓口で提示することとなります。
現物給付化の適用を受けない場合には、自己負担限度額を超えた額が払い戻されるまで3〜4ヶ月程度かかっているため、外来診療にも現物給付化が広がったことにより被保険者の負担が少なくなります。
19年4月から入院について、窓口での支払を自己負担限度額までとする現物給付化が行われていましたが、24年4月1日からは外来診療についても現物給付化が始まりました。
高額療養費の現物給付化の適用を受けるためには、事前に限度額適用認定証の申請をしておき、それを医療機関等の窓口で提示することとなります。
現物給付化の適用を受けない場合には、自己負担限度額を超えた額が払い戻されるまで3〜4ヶ月程度かかっているため、外来診療にも現物給付化が広がったことにより被保険者の負担が少なくなります。
パソコン専用メガネ
パソコンやスマートフォンの普及によってディスプレイを眺める時間が増えています。
パソコン専用メガネは、パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイから発せられる「ブルーライト(紫外線に最も近い性質を持った可視光線)」を大幅にカットするという効果があるようです。一度お試しされてはいかがでしょうか。
パソコン専用メガネは、パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイから発せられる「ブルーライト(紫外線に最も近い性質を持った可視光線)」を大幅にカットするという効果があるようです。一度お試しされてはいかがでしょうか。